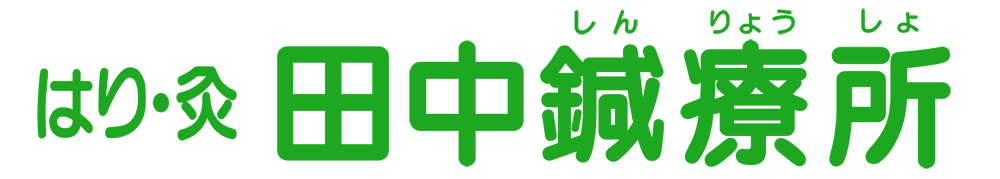お知らせ
秋の養生法

今年の秋は立秋8/7から立冬が11/7までの3か月間です。
陽気が減り陰気が増えていく、冬を迎える準備をする季節です。
秋は肺を労わろう🍂
東洋医学では、秋は肺の機能が活発になると考えます。
肺は呼吸によって全身に気を巡らせる臓で、滋潤、温暖を好み、乾燥や寒さを嫌う特徴があります。
また、肺は生きている間休むことなく、膨らんでは縮んでという運動を繰り返しています。この相反する肺の働きを「宣発作用」と「粛降作用」といいます。
→ 宣発作用 肺が縮んだ時に、気と水、他にも栄養分や体を守る免疫機能を全身に巡らせる作用
→ 粛降作用 肺が膨らんだ時に、要らなくなった不必要なモノを体の下に降して排泄させていく作用
秋の邪気と肺🫁
秋の邪気は燥邪、つまり乾燥です。
慈潤、温暖を好む肺に燥邪が侵入すると、 肺の働きが悪くなり、咳や風邪などの呼吸器系のトラブル、皮膚・唇・髪の乾燥や便秘などが現れやすくなります。
また、秋の気候の前半はまだ夏の暑熱が残っているところに、秋の主気である「燥」が加わり「温燥」になり、晩秋になると冬の主気の「寒」が加わりその燥は「涼燥」となるため、それぞれに合わせた養生が必要になります。
秋は早寝早起きをして心身共に安らかに安定した気持ちで過ごすことが大切です。
秋の燥邪は肺を傷めやすいため、津液を補い脾胃の調子を整えることが大切です。
秋を健やかに過ごす養生法
秋の邪気の燥邪に上手く対応できれば、心地よく秋を過ごせ寒い冬に向かって体を整えていくことができます。
体温調節
秋は一日の中でも季節を通しても寒暖差が大きくなります。また、冷房が効き過ぎて寒かったり、逆に暑かったり、湿度も高かったり低かったりもします。サッと羽織れる上着を一枚準備されることをお勧めします。
喉や肺を守る
乾燥による呼吸器へのダメージを防ぐため、こまめにうがいをして喉を潤おすようにしましょう。そうすれば、肺や呼吸器は清気を吸い込み濁気を吐き出すという体のバリア機能が充分な働きをしてくれます。
ストレスを溜めない
肺は憂いや悲しみの感情の影響を受けやすいため、心静かに、気持ちをできるだけ平穏に保ち、心配事や悲しみで感傷的にならない。もし、そのような気持ちになったら、カラオケなどで大きな声を出して発散しましょう。