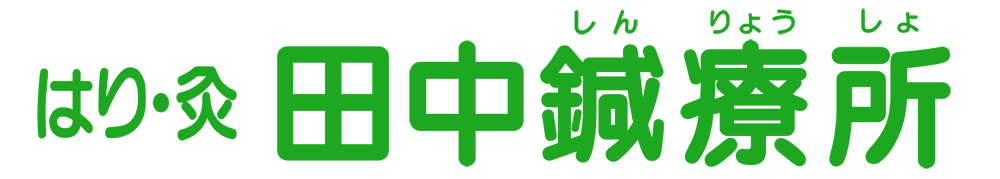お知らせ
季節のお身体トラブル《睡眠障害》

春になると、
なかなか寝付けない、眠りが浅い、たくさん寝ても寝た気がしない、疲れているのに熟睡できない、夢を多く見る、夢で疲れる、夜中に何度も目が覚める
こんなことが多くなります。
東洋医学では
東洋医学では、体の中の陰気と陽気がバランスよく切り替わることで良質な睡眠が得られると考えています。
陰陽の切り替わりとは、昼間活動している時は、目や頭、骨格筋に陽気が集まり活発に行動でき、夜、眠りに付くころには陽気は内臓を中心とした内に入り、逆に目や頭に陰気が集まり体は沈静化すると考えます。
春に睡眠障害が増えるのは、この陰陽の切り替わりが、春特有の寒暖差や強い風、または、新年度の環境の変化によるストレスなどで乱されるためです。
睡眠障害の種類
《寝つきが悪い》
寝つきは胃腸と関係が深いと考えています。
お腹がいっぱいだと眠くなる。お腹が空いていると眠れない。これは誰しも共感いただけることだと思います。
睡眠障害における寝つきの悪さは、このお腹が空いている状態と同じです。これは実際にお腹が空いているのではなく、胃に熱を持つとお腹が空いた状態と同じになるので寝つけなくなります。
《夜中に目が覚める》
眠りにつくと、2~3時間後に体が温まり深い眠りに入っていきます。
しかし、普段から「のぼせ」が強く、頭や上半身に熱が多いと、深い眠りについたときの体温が、最初からあるのぼせと重なり、寝ついてから2~3時間後に眠りが浅くなり目が覚めてしまいます。ひどい時は、毎日同じ時間に目が覚めるようになります。
春の寒暖差はこの「のぼせ」を助長します。まだ夏のように発汗することがない春は、温かい日は頭や上半身に熱が強くなり、気温が低いには手足が冷やされ、さらにのぼせが強くなる、というわけです。
《朝早くに目が覚める》
まだ寝ていたいのに朝早くに目が覚めてしまう。睡眠時間は足りていないのに朝方目が覚めた後は寝つけない。
高齢になると朝早くに目が覚めてしまう事は有りますが、若い方でも同じ事が起きます。
《夜中に目が覚める》で、春の寒暖差がのぼせや冷えを助長すると記述しましたが、発汗などの代謝の悪さからむくみなど、体内の水分バランスも悪くなります。
その結果、夜中に体が温かくなると、水分を余分に消耗し、口渇などを伴い起床時間よりも1~2時間早く目が覚めてしまいます。
《夢が多い》
夢は眠りが浅いレム睡眠の状態で多くなります。
夢は誰でもみているそうです。しかし、それを覚えている、覚えてはいないけどうなされるなどは、眠りが浅いといえます。
東洋医学では、春は肝臓(肝)が元気に働いて血を巡らせる季節だと考えます。肝に不調が起こると、血の巡りが悪くなり、常に頭に血液が停滞し、頭を働かせている状態になります。その為、寝ていても考え事をしてしまい、考えている事が夢に出て、眠りが浅くなります。
ちょこっと対策
日本人の平均睡眠時間は7時間程度とされていますが、個々で必要な睡眠時間は異なり、3時間でしっかり寝たと満足する人もいれば、8時間以上寝ないと体がだるいなどの体の不調を訴える人もいます。
睡眠の時間に関してはかなり個人差があるものです。
その上で、夜間に長期で不眠の状態が続き、日常に睡眠障害からくる不調を感じるようになった場合には、不眠症との診断がされます。
不眠への対処には
○就寝時間を一定にする(睡眠時間、起床時間を一定にする)
○睡眠時間にこだわらない(眠れない場合は起きてしまう)
○太陽光を浴びる
○適度な運動
等の解決法があります。
最近皆さんがしがちなのが、就寝前に電気を消したベッドの中で携帯を見る習慣。
通勤時も昼休みもスマホを見る習慣があるように、寝る直前までスマホを見ていることで
寝ようとする脳に対して、眼からの情報で脳が覚醒してしまい、睡眠状態は悪くなります。
脳を覚醒させる行動ではなく、できるだけリラックスさせて短時間であっても質の良い睡眠をとるようにすれば翌日もスッキリするはず!