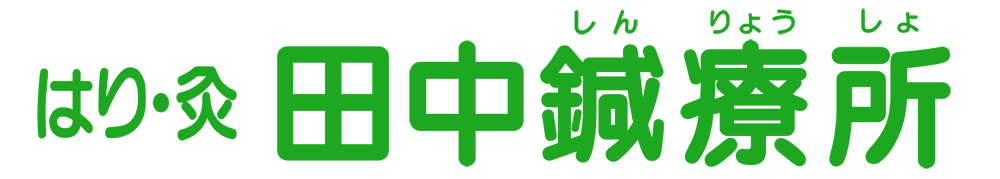お知らせ
季節のお身体トラブル《梅雨(気象病)》
そろそろ梅雨入りかな?と調べてみると、東海地区の平年の梅雨入りは6月6日頃。
しかし、昨年2024年はなんと、6月21日と随分と遅かったようです。
まあ、そんな年もありますが、徐々に近づく梅雨。
梅雨は髪がボワっとまとまらないし、体はだるいし苦手という人は多くいます(私もその一人)。
髪がまとまらないは関係ないとして、最近「気象病」なんて言葉を耳にしたことのある方も多いのではないのでしょうか?
天気痛や季節病などとも呼ばれているこの病気は、その名が示すとおり、天気の変化が影響して身体や精神に起こるさまざまな症状のことで、特に梅雨時に多く見られる傾向があるようです。

気象病の原因
気象病が発症するメカニズムはまだ解明されていません。しかし、以下の要因が関係して自律神経に影響をおよぼすことが、主な原因だと考えられています。
1、気圧
気圧は体にかかる空気の圧力。これに対し体は内側から同じ力で圧を発しています。
ところが、季節の変わり目や台風などによる気圧の変化で、この調整がうまくできなくなり、自律神経の乱れのほか、身体への圧力が弱まって血管が拡張し、気象病を引き起こすと考えられています。
2、気温
季節の変わり目や寒暖差は、自律神経の調節が追いつかずにバランスを崩しやすく、不眠や倦怠感、めまいなど、症状が悪化しやすくなることがあります。
春先の冬の寒さから徐々に春めいてくる気温変化に反応する人と、秋口の夏の暑さから秋の肌寒さの変化に反応する人の2パターンがあるように感じます。
3、湿度
気象病の原因には、湿度も関係していると考えられています。
湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、体の水分の代謝が悪くなるため、のぼせやむくみなどで体温調節がうまくできなくなることがあります。その結果、痛みなどが起こる要因になります。
梅雨に感じる症状
特に多いのは「頭痛・頭重感」および「疲れ、だるさ」で、ほかに「首や肩のこり」も梅雨時の不調として男女共に多い傾向があります。
しかし「気分の落ち込み、不安感」や「眠気」、「めまい」、「吐き気」といった症状については男女間で大きな違いがあり、女性の割合は男性の約2倍もしくはそれ以上といわれています。
東洋医学から考える梅雨の体調不良
東洋医学では、こういった気圧や気温の変化で悪化する場合、「水毒」が関わっていると考えます。
「水毒」とは、身体の中の水分バランスが乱れ、頭痛・頭重感、むくみ、痛み、吐き気、めまい、耳鳴りなどさまざまな症状を引き起こしている状態を指します。
下記のチェックリストに1つでもあてはまる方は、「水毒」体質かもしれません。
⬜︎めまいや立ちくらみを感じることが多い
⬜︎頭痛や頭重感(頭がダル重い)を感じることが多い
⬜︎耳鳴りがする
⬜︎冷え症である
⬜︎車酔いをしやすい
⬜︎からだのむくみが気になる
⬜︎下痢をしやすい
⬜︎上記のような症状が季節や天候の影響で悪化する
対処法
日本では古くから「食養生」といって、身体が求める食事を正しく選ぶことで、健康を維持していくという考え方があります。
日々の食事で、「水」のめぐりを整える食材を取り入れてみるのもおすすめです。
カボチャ、トウモロコシ、大豆、小豆、キュウリ、スイカ
鍼灸治療はこの「水毒」に対応します。「胃腸機能の改善」や「発汗・排尿などの代謝向上」、「呼吸機能の改善」、とお一人お一人の体質、状態に合わせて施術いたします。
梅雨の体調不良には、是非、鍼灸治療をご活用ください!